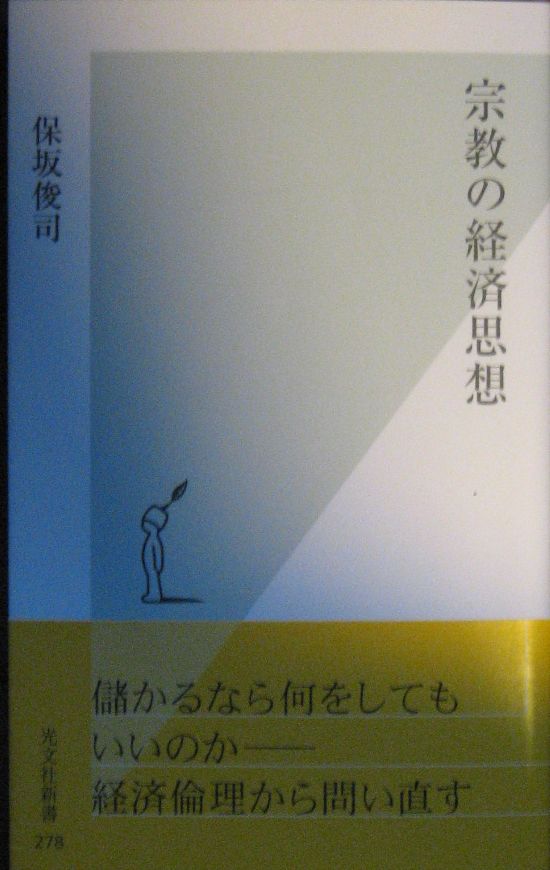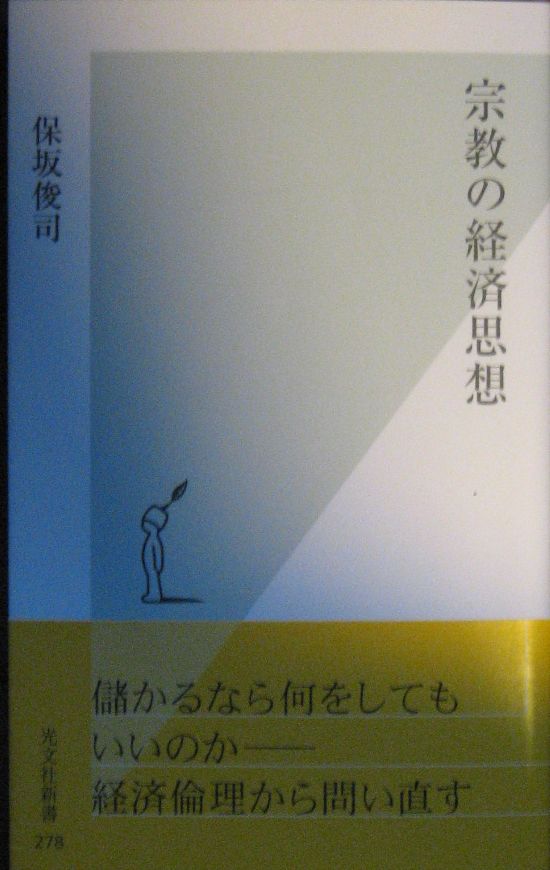|
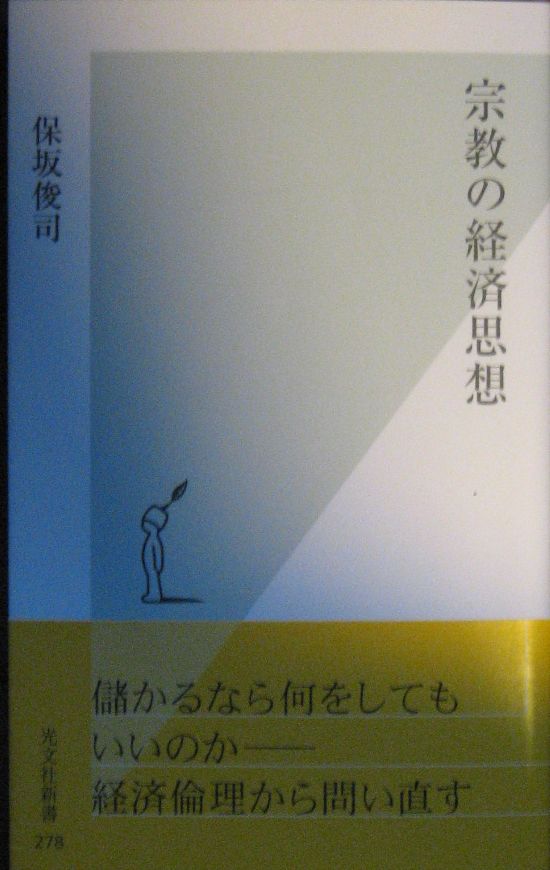
(『宗教の経済思想』光文社新書)
〜『宗教の経済思想』〜
○宗教的倫理が不祥事の土壌を
ここに『宗教の経済思想』という本がある。キリスト教、イスラム教、仏教、そして日本の経済思想について、歴史的に比較し丁寧に解説したものだ。なかなか参考になり、教えられる。
ただ、一点だけ、そしてとても大きな点なのだが、どうしても著者の保坂俊司さんの視点に異を唱えておかなければならないころがある。
こういう視点にたいしてだ。
「今日資本主義経済社会が抱える問題の多くが、宗教倫理の欠如にあるということは、誤りのない視点であろう」。
宗教(あるいは宗教的といってよい)倫理の欠如こそが、バブル崩壊後の経済界でのさまざまな不祥事を生みだしている、と著者は指摘する。
わたしにはまったく逆に思える。ひとつは宗教倫理こそが資本主義の抱える問題をより惹起し、あるいは拡大してきたのではないか、と。また宗教倫理こそが、社会が抱えるしくみの問題を結果として隠蔽し、矛盾をさらに拡大する役割を果たしてきたのではないか、と。
わたしは宗教を「阿片」などととらえる蒙昧から多少は自由なつもりだ。むしろ宗教のなかに人間の心の動きが集約されている。ものごとを突き詰めたり、存在を振り返るとき、つねに宗教(的発想)と向きあうことにもなる。宗教を貶めようという気持ちはもたない。
ただ、宗教倫理の欠如が資本制経済社会での不祥事を生みだしたのだとは思わない。逆に、宗教的倫理こそが不祥事を生む土壌をずっと醸成しつづけてきたのだ、ととらえる。
○宗教倫理が推進してきた
労働とは苦役であり、できれば奴隷(他者)にさせたほうがよい、できれば短時間ですませたいという古来からの労働観がある。これは宗教ではないが、古来からの西欧に根強い発想だ。労働は他者に押しつけるか、手っとり早く済ませればよいという考えが職場や環境を荒廃へ近づけている。
たほう、「時は金なり」なのだから、倍々で増殖する貨幣(と膨大な財産)を生み築くために、寸暇を惜しんで働こうという効率優先の労働観がある。倍々で利潤を増殖させていくべきであるという考え方が、経済界における不祥事の発生をより促進してきたことを否定することはできない。
あくなき利潤の追求を促すのは、「時は金なり」の思想であり、仕事を神から授けられた天職として休みなく全うしようとする天職思想だ。
寸暇を惜しんで働き利潤を増殖させることこそ務めとする思想と組みあわせられた利潤増殖の自己運動こそが転倒を呼びこみ、「倫理性の軽視や欠如が原因と思われる不祥事」を生みだすように結果しているのであって、宗教倫理の欠如がそれを生みだしているのではない。
人間は弱い存在だ。だからこそ、利潤の自己増殖運動に巻きこまれて、脱法や法の侵犯へと向かってしまう。向かうように強いられる。
むしろ、目を向けるべきは、そのように強いてしまう、利潤の自己増殖運動の力学だ。そのしくみから目を背けて、心や信仰を問い、倫理や道徳を説き守らせようとすることに収斂するのは、問題を不可避に惹きおこす、根っこにあるしくみを支えることになる。
○崇高なる「善意」と飽くなき利潤追求
莫大な利益を上げ個人資産を蓄積した人が、たとえば福祉へその財産を寄付すること、保坂さんはそこに「損得勘定を超えた崇高な価値観、特に宗教性があるのではないか」とみる。
果たしてそうだろうか。
その「善意」をあえて否定することは止めよう。けれども、膨大な寄付行為を可能にする莫大な利益と資産がどのようにして生まれたのか、にも目を向けるべきだろう。あくなき利潤の自己増殖運動を推進しなければ、それは生まれやしない。それは屈指の資産家のビジネスを辿れば明らかなことだ。生産することより増殖する貨幣にものいわせて他組織を傘下に収めることを次々にくりかえす金融力こそが膨大な利益・資産を生みだした、といっても過言でなない。脱法すれすれの、つねに充足をよしとしない、苛烈な飽くなき利潤追求運動があればこそ、巨額の利益・資産を転がりこませてきた。
利益・資産の巨大性は、狭い地域を超え、国境を越え、いわばグローバルスタンダードとなるからこそ生まれもする。そうして得られた利益から蓄財された資産の一部、または全部が寄付される。
あくなき、慈悲なき利潤追求と、巨大な善意、巨額の寄付は一体のものであるということだ。
誤解をしてほしくないのだが、いま個々人の心の善意、たとえば寄付者の善意についてあれこれ言いたいのではない。個々の経営者であったり、資本家を批判したいのではない。ここで倫理やモラルを持ち出して個々の批判をすることは、宗教倫理の欠如を指摘する論と同じ土俵に乗ることになる。
むしろ明確にさせたいのは、いわば法すれすれ、あるいは脱法行為的経営や、遵法でも下請けや非正規雇用者などにより多くの犠牲を強いたりしながらだからこそ、より利潤を蓄積でき、膨大な寄付を生みだす財をなすことができるということだ。また、グルーバル化が進む状況下ではなおさら、そうした施策を強いられることだろう。
つまり寄付としての善意と、「経済効率を優先させる利益至上主義」とは表裏一体だということだ。今こそ問題とされるべきは、表裏一体のしくみ、そしてその基盤を補完したり強固にしてしまうような発想自体を疑ってみることだ。
○「利他」を説く危うさ
日本では欧米とは異なる宗教観が育まれてきた。労働を苦役とはしない考え、労働を神聖なものととらえる考え、日常のさまざまな所作のなかに宗教的な心を観る考えなど、欧米のものとは違う労働観が流れてきたことを、保坂さんは指摘し、教えてくれる。
ときの為政者に利用されたりすることもあったろうが、そうした労働観には吸収するべきところも少なくないと思われる。
ただ、立ち止まって考えておきたいことがある。それは「利己」と「利他」を対比させ、利己のためではなく、あるいは利己ばかりのためではなく、利他のためにあろう、働こうではないかという言説である。
他者のために尽くすという倫理や道徳は否定されるべきではなく、大事なことではあるけれど、それは世界の半分に関しての言説にすぎない。どんなに利他を説かれても、ひとは弱い存在であるから、利己に走らざるをえないことが往々にしてある。それは人間が避けようもなく強いられる存在のありようだ。とりわけ、資本制社会、このポスト産業資本主義社会では、利潤の自己増殖のために、ひとはその歯車と化してしまっている。そのように存在を強いられた中で、利他の精神や倫理をいくら謳っても、それは半分の力しかもたない。
それでも無理矢理利他を説けば、危険な大義に転化する。そうした大義や正義がどれほどの転倒と悲惨を生んだかは、二〇世紀がうんざり示してくれていることだ。
たまたま保坂さんの書について触れて語ることになったが、ほとんどの識者たちはモラルや心を語る言説に終始している。近頃では経済学者すら、経営倫理を語ることに腐心している。
そうではなく、ひとが否応なく巻き込まれる苛烈な資本の自己増殖運動自体をどうとらえるのか、あるいはそこでの働き方のしくみなどにこそ、目を向けるべきときに来ているのではないか。
(2006-12-16)
|
 |