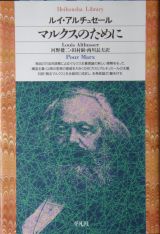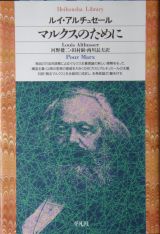|
 |
スローワーク論
(ノート) |
 |
理論と実践とは弁証法的統一のもとにある、
とは学者の寝言で、もともと理論と実践と
は同じものだ。
(小林秀雄「マルクスの悟達」)
|
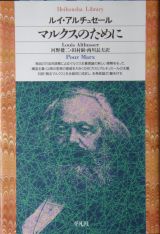
本「スローワーク論」をベースに、大幅に改稿し、
『労働止揚論』を上梓しました。
(536ページ、税別2,700円、amazonで販売)
購入はこちらへ
70 アルチュセール「認識論上の切断」で捨られたこと
マルクス(5) |
○四五年の「認識論上の切断」
フランスの「マルクス主義」哲学者、ルイ・アルチュセール(1918〜1990年)さんは、青年期マルクスの著作と、『資本論』のあいだには根本的差異があり、それは一八四五年ごろの「認識論上の切断」にはっきりみられることを指摘する。青年期のイデオロギー的「プロブレマティック」(問題設定)と、『資本論』の「プロブレマティック」のあいだには根本的差異があるとしている。
一八四三年の『ヘーゲル国法論批判』、『法哲学批判序説』、四四年の『経済学・哲学草稿』などをひっくるめて、彼は、若きマルクスのヘーゲル批判についてつぎのように書いている。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ところで、このヘーゲル批判は、当時、その理論的な原理においては、フォイエルバハによってくりかえし定式化されたすぐれたヘーゲル批判の再現であり、注釈であり、あるいはその展開または拡張以外のなにものでもない。このヘーゲル批判は、思弁として、あるいは抽象としてのヘーゲル哲学にたいする批判であり、疎外という人間学的プロブレマティックの原理の名におこなわれた批判、思弁的抽象性を拒否し唯物論的具体性をもとめる批判、すなわち観念論的プロブレマティックから解放されることを望みながら依然としてそれにとらわれた批判、したがって当然のことながら、マルクスが四五年に断ち切ることになる古い理論上のプロブレマティックにいまだ属している批判である。
(アルチュセール『マルクスのために』
河野健二・田村俶・西川長夫訳)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
『経済学・哲学草稿』を含めて、四四年までのマルクスが「抽象的思弁性」にとらわれた「古い理論上のプロブレマティック」にあったことを強調している。
そして彼は、四五年に書かれた『フォイエルバッハにかんするテーゼ』『ドイツ・イデオロギー』をマルクス切断期の著書ととらえ、そこに「明確な認識論的切断」をみて、切断期の著作こそ「哲学的(イデオロギー的)な自分の古い意識にたいする批判」が展開されたものと線を引いている。
それまでのマルクスが、「二、三年のあいだはフォイエルバッハのプロブレマテイックそのものに文字通り加担したこと、マルクスはフォイエルバッハに深く同一化したこと」を指摘している。
○「切断」したかった狙い
彼のいう「認識論上の切断」の是非はひとまずおき、彼がこれを強調する狙い、背景を先にみてみよう。
アルチュセールさんが四五年段階におけるマルクスの「認識論上の切断」にこだわるのは、当時勢いをもっていた、「哲学的ヒューマニズム」を「イデオロギー」として批判し、真の「マルクス主義」を再生させたかったからだ。「人間」をあらゆる理論の原理とする「哲学的ヒューマニズム」は「ブルジョア的ヒューマニズム」にほかならない。「マルクス主義哲学」「史的唯物論」の確立こそ、マルクスが果たしたことであり、それを復活さ、「政治的実践」を通じて「理論と実践の統一」を図らなければならないことになる。
このとき、「疎外」論は、彼の眼には「ブルジョア的ヒューマニズム」というイデオロギーとして邪魔物以外のなにものでもない。「イデオロギー」は「科学」ではない。イデオロギーのなかでこれにとらわれているかぎり、史的唯物論(科学)を認識できない。彼にとって最大の課題は「真のマルクス主義理論」の構築であり、それと「労働運動の統一」であり、「科学的認識」にほかならない。
○「認識論上の切断」はあったのか
では、アルチュセールさんが指摘するような「認識論上の切断」がマルクスにあったのだろうか。
彼が挙げる「切断期」の著述として、『ドイツ・イデオロギー』とともに「フォイエルバッハに関するテーゼ」がある。よく知られるように、「哲学者たちは世界をさまざまに解釈してきたにすぎない。重要なのは世界を変えることである」というテーゼで結ばれたものだ。
そこでのフォイエルバッハ批判を二、三、挙げてみよう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
従来のあらゆる唯物論(フォイエルバッハのそれも含めて)の主要な欠陥は、対象が、つまり現実、感性が、ただ客体ないし直観の形式でのみ捉えられ、感性的・人間的な活動、実践として、主体的に捉えられていないことである。
(マルクス「フォイエルバッハに関するテーゼ」岩波文庫版)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
フォイエルバッハは宗教の本質を人間の本質へと解消する。しかし、人間の本質とは、個々の個人の内部に宿る抽象物なのではない。それは、その現実の在り方においては、社会的諸関係の総体(アンサンブル)なのである。
(マルクス「フォイエルバッハに関するテーゼ」岩波文庫版)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
これらのフレーズは、たしかに四五年ごろから強くうちだされる。しかし『経済学・哲学草稿』のなかにこれらが置かれていたとしても異和を感じることはない。いいかえれば、四四年と四五年に切断線を引くのはむずかしい。
現にマルクスさんは『経済学・哲学草稿』でこう書いている。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
労働者は、自然がなければ、感性的な外界がなければ、なにものをも創造することができない。自然すなわち感性的な外界は、労働者の労働がそこにおいて実現され、そのなかで活動し、それをもとにしそれを介して生産する素材である。
(マルクス『経済学・哲学草稿』城塚登・田中吉六訳)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
労働が、「フォイエルバッハに関するテーゼ」にある「感性的・人間的な活動、実践として、主体的に捉えられて」いる。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
社会そのものが人間を人間として生産するのと同じように、社会は人間によって生産されている。
(マルクス『経済学・哲学草稿』城塚登・田中吉六訳)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
これは人間のとらえ方を「社会的諸関係の総体」とすることにつながっている。
ほかにも、「国民経済学者たち」が社会(市民社会)における関係性を、「人間」つまり「個人に還元し」、「この個人からあらゆる規定性をはぎとるのである」と批判しているが、これも四五年のテーゼとつながる。
また、同年から書かれた『ドイツ・イデオロギー』で、「彼らが何であるかということは、<それゆえ、彼らの生産様式の内に示される>それゆえ、彼らの生産と合致する。すなわち、彼らが何を生産するか、<同様に>ならびにまた、彼らがいかに生産するかということ<の内に示される>と合致する。それゆえ、諸個人が何であるかということは、彼らの生産の物質的諸条件に依存する」とあるのは、『経済学・哲学草稿』の視点をより具体化したにすぎない。
つまり、「認識論上の切断線」を引いて、きれいさっぱりさせることなどできはしない。
○四四年のマルクス
フォイエルバッハは、人間が自己の本質を神として措定しているにすぎない、としたうえで、疎外された表象にすぎない神を人間の本質ととらえなおして自己疎外を克服すべきであるととらえた。このときフォイエルバッハのいう人間とは、「感性的」「自然的」という抽象で規定された「一般的人間」でしかなかった。たしかにマルクスは四三年当時、フォイエルバッハのこの人間主義に立っていた。
だが、受け継ぐと同時に、すでに四四年の草稿で、フォイエルバッハのそれとは異なる地平に踏みだしている。人間とはフォイエルバッハにあっては、感性的・自然的な一般的規定としてとらえれらる一般的人間にすぎなかったが、マルクスは市民社会における歴史的現実(生産的諸関係)に規定されたものとして明確にとらえている。同様に、疎外も、市民社会における諸関係のなかでとらえられている。労働、交換、所有、分業、信用という具体的な社会的・経済的諸関係をもとに論じられる。
いったい、アルチュセールさんは『四四年草稿』(『経済学・哲学草稿』)をほんとうにしっかり読みこんでいるのだろうか。そんな問いはまことに失礼なことだし、いくらなんでもまさかそんなことはないだろうと思いつつ、その疑念は晴れない。
『マルクスのために』では、『ユダヤ人問題』『ヘーゲル国家哲学批判』などは登場しても、『経済学・哲学草稿』を読みこんでいたと思われるフレーズは出てこない。フランス語化した訳者ボッティジェリ氏を礼讃しながら、訳者解説に即して説明しているのだが、アルチュセールさん自身の読みこみはうかがえない。みえるのは、人間が「あるべき本来の自己」の回復という、変形された自己疎外論を批判しているだけだ。
少し触れているものとして、次のような原注が施されている箇所がある。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
『四四年の草稿』では、人間の本質の客観化は、人間による人間の本質の再獲得に不可欠な与件として容認されている。客観化の全過程をつうじて、人間は客観性の形式においてのみ実在し、その形式のなかで人間は、無縁で非-人間的な本質の外観のしたに自分自身の本質と出会う。
(アルチュセール『マルクスのために』
河野健二・田村俶・西川長夫訳)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「人間の本質の客観化は、人間による人間の本質の再獲得に不可欠な与件として容認されている」と図式化しているが、そもそも「人間の本質の客観化」などとはマルクスは定義していない。
「人間は客観性の形式においてのみ実在し」なとども書いていない。自然と人間との相互に規定しあう関係性について鋭く分析しているものの、「客観性の形式においてのみ」などと硬直した主体・客体関係のとらえ方には立っていない。それはアルチュセールさん自身の頭脳の反映ではないだろうか。このとらえ方は、のちの『再生産について』でも基本的には変わっていない。
○「マルクス主義」のプロブレマティック
アルチュセールさんは次のように考える。マルクスは、フォイエルバッハのヘーゲル批判を不徹底なものととらえた。つまりヘーゲルの世界に留まっていて、「ヘーゲルの根本原理」に依拠しながらの批判にすぎない。フォイエルバッハは「エレメント[住みか]を変えはしなかった」と。
これにたいしてマルクスによって、「ヘーゲルにたいする真のマルクス主義的批判はまさしく、エレメントが変えられたこと」と。
だが、ことはそう簡単ではない。マルクスがヘーゲルに依拠しているところは多々ある。同時に、絶対知や国家に収斂されていくヘーゲルの観念過程を厳しく批判した。
『経済学・哲学草稿』でマルクスのヘーゲル評価を端的に示してみよう。
ヘーゲルが「労働を人間の本質として、自己を確証しつつある人間の本質ととらえ」ることを評価しつつ、「その肯定的な面を見るだけで、その否定的な側面を見ない」と批判する。
対象化を対象剥離ととらえた(疎外の概念)のがヘーゲルの「偉大な」ところとしつつ、「自己外化および自己疎外としての自己産出、自己対象化」の運動、過程が絶対精神の生成としてとらえられて回収されてしまうことを痛烈に批判した。
厳しく批判しつつも、現実の社会的諸関係のなかでの活動(労働)を人間の本質ととらえる視点、疎外の概念はヘーゲルから受けとめ、それは終生変わることはなかった。
人間は、先達の叡智、あるいは自己の過去の営為を簡単にきれいに「切断」などできやしない。さまざまな変化、変遷はあっても、ある地点をもって「切断」などできやしない。
一方、ヘーゲルを批判するアルチュセールの「マルクス主義」は、ヘーゲルのやり方以上に自己完結的なものだ。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
マルクス主義はそれ自体、認識論の問題の対象でありうるし、またそうでなければならないということ、さらにこの認識論の問題は、マルクス主義理論のプロブレマティックとの関連においてのみ提起されうるということ、このことは単に歴史科学(史的唯物論)としてのみならず、また同時にさまざまな理論構成の性質とその歴史を解明できる、つまり自分自身を対象とみなすことによって自分自身を解明することができる哲学として、自己を弁証法的に規定する一個の理論にとってまさに必然である。マルクス主義はこうした試みに理論的に立ちむかう唯一の哲学である。
(アルチュセール『マルクスのために』
河野健二・田村俶・西川長夫訳)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ここで語られているのは、「マルクス主義」理論のプロブレマティックに立たなければ、認識論の問題は提起できない。マルクス主義は「つまり自分自身を対象とみなすことによって自分自身を解明することができる哲学」であり、それは旧来の「イデオロギー」のなかにあってはみえない。しかし、「科学」(階級)の立場にたてば「イデオロギー」をイデオロギーとして把握できる、と。「マルクス主義」は「自分自身を対象とみなすことによって自分自身を解明」できる。他を排除した自己運動としてある。これは「マルクス主義」が信の問題に帰着することを如実に示しているにすぎない。
○歪められた「疎外された労働」
具体的に「疎外された労働」論をみてみよう。
労働の対象素材が自分のものではない、労働の過程が自分のものではない、労働の生産物も自分のものではない。このことをマルクスは「疎外された労働」(「労働における疎外のかたち」)としてとらえた。この社会経済的現実の労働を仔細にとらえれば、そうみえるのはごく自然のことである。
同時に、その事実の認識は、そうではないはずではないか、という問いとともにある。労働の対象素材はなぜ自分のものではないのか、労働の過程はなぜまず自分のものではないのか、なぜ労働は命じられるものでしかないのか、自らがつくったもの(生産物)がなぜ自分のものではないのか。かりにそのあと手から離れるにしても、生産したもの自体、なぜ自分の手に入らないのか。
現前する自体の認識は、それを否定(止揚)しようとする意思とともにある。疎外は疎外止揚とともにある。
しかし、アルチュセールさんによると、次のようになる。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
……、疎外された労働という鍵になる概念はあたえれらた理論的な規定と理論的な役割について考察し、この観念が概念上かかわる領域を検討しなければなるまい。そして、この観念は、当時マルクスがそれにあたえた役割、つまり、原初の基礎という役割を立派に演じていること、ただしこの観念がこの役割を演じることができるのはただ、「人間」という概念全体――われわれになじみ深い政治経済学の諸概念の必然性と内容が、やがて人間の本質からひきだされるもとになる――の委託された任務として、この役割をうけいれるという条件のもとにおいてだけであることを認識しなければなるまい。
(アルチュセール『マルクスのために』
河野健二・田村俶・西川長夫訳)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「疎外された労働」という「観念」、とらえ方は、「原初の基礎」としての「人間」という役割があって初めて成立するもののほかならない。そして、「労働から疎外された生産物(商品、国家、宗教)」に宿る「人間固有の本質を、主体として」取り戻せば「真の人間」になれる、と「古い」マルクスは説いている、とアルチュセールさんはとらえている。要するに、「原初の基礎」としての「人間」、本来あるべき「人間」の姿、本来的自己が措定されているととらえる。これはマルクスの疎外論ではないのだが、曲解した「本質からの疎外」論を標的にする。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
労働から疎外された生産物(商品、国家、宗教)のうちに、人間はそうとは知らずに、人間の本質を実現している。人間のこうした喪失が、歴史と人間とを生みだしているけれども、実はその前提として、あらかじめ実在している明確な本質があったのだ。人間性を喪失せる客観性と化したこの人間は、歴史のおわりには、財産、宗教、国家のうちに疎外された人間固有の本質を、主体として、もはやとり戻しさえすればいいのだ、――全体的人間、真の人間となるために。
(アルチュセール『マルクスのために』
河野健二・田村俶・西川長夫訳)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
これはフォイエルバッハへの批判としては当たっても、マルクスにはあてはまらない。「人間固有の本質を、主体として、もはやとり戻しさえすれば」「全体的人間、真の人間」となる、といった楽天的な疎外論にマルクスは立っていないことはすでにみたとおりだ。人間の諸活動はつねに疎外とともにある。疎外が諸活動を生む。「人間固有の本質」をとり戻した「真の人間」の状態をユートピアとしてくくりだすものではなかった。
マルクスが『経済学・哲学草稿』で「疎外された労働」として分析してのはすでにみたように、現にある社会的・生産関係のもとで、労働がどのように強いられているのか、それを分析したのにすぎない。先に挙げた「フォイエルバッハに関するテーゼ」にある「人間の本質とは、個々の個人の内部に宿る抽象物なのではない。それは、その現実の在り方においては、社会的諸関係の総体(アンサンブル)なのである」とのとらえ方を前提にして、「疎外された労働」論が展開されているにすぎない。
では逆に、アルチュセールさんの立場に立ったとき、労働過程が労働主体のものに属していないことはどのように批判できるのだろうか。どこに根拠をもつのだろうか。
しばしば引用されるように、『ドイツ・イデオロギー』では、「共産主義というのは、僕らにとって、創出されるべき一つの状態、それに則って現実が正されるべき一つの理想ではない。僕らが共産主義と呼ぶのは、<実[践的な]>現在の状態を止揚する現実的な運動だ」(廣松渉編訳・小林昌人補訳)とある。まさに疎外と疎外止揚の運動をとらえたものだ。
とすれば、いったいアルチュセールさんは、「現在の状態」を「止揚」したいとすべき根拠をどのようにしてどこに求めることができるのか。
彼の意識のなかには応えは用意されている。「科学的認識」であり、「真のマルクス主義」であり、「唯物史観」だ。
○媒介なき理論は「大衆」に逃げこむ
アルチュセールさんのこういう「ヒューマニズム」のイデオロギー批判から発せられた「認識論上の切断」論が、二〇世紀後半いつの間にか一部で「定説化」されてきた。不思議なことだ。しかも晩年の彼は自ら「認識論上の切断」について自己批判的に言及することになる。
西欧知とそれになびいてきたわたしたちの病いは、ますます深い。そもそも「マルクス主義」という絶対観念に拘泥し信仰し続けた揚げ句のことだ。
彼は「反ヒューマニズム」としてのマルクス主義の理論こそが、認識と実践の変革を可能にする、という。
たとえばこういうフレーズがみられる。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
すなわち人間についての哲学的(理論的)な神話を焼きはらい灰燼に帰せしめるという絶対的条件においてのみ、人間についてなにごとかを認識できるのだ。
(アルチュセール『マルクスのために』
河野健二・田村俶・西川長夫訳)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
もはや現実との媒介を失っているゆえに記されることが可能なものではないか。理論上のことを指しているのだが、それにしてもどんな行為やテロリズムも許される可能性を孕むフレーズだ。「党」の人間、「戦闘的知識人」らしい。
ヒューマニズムを批判したから(「反ヒューマニズム」だから)、テロリズム的思考に陥るのではない。現実を全否定する(できてしまう)「科学」理論、いいかえれば媒介をもたない論(「マルクス主義」)に依拠するから、現実を容易に全否定できる。党の理論家、戦闘的知識人の頭脳は現実をいかようにも否定できる。
そして媒介をもたないゆえに不安に駆られた観念は、最後は「理念化された大衆」に逃げこむ。どこの国の「マルクス主義」も同じことだ。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
マルクス主義理論と労働運動の統一は、一方では理論(認識)と関わりつつ、他方では能動的・歴史的現実、すなわちプロレタリアートおよび人民大衆と関わることになるが、マルクス主義理論と労働運動の統一を考えるためには、「歴史を作るのは大衆である」というマルクス主義の根本原理を忘れてはならない。
(アルチュセール「批判的・自己批判的ノート」市田良彦訳)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
労働運動はしたがって、具体的、歴史的現実、「歴史を作る大衆」に根を下ろした現実を指示している。大衆とは書物の中に存在するのではなく、生活の中に存在するのである。大衆が「書物から外に出ない」ことはありえないし、大衆は必ず「生活の中に入る」。というのも、大衆が生活であるからであり、最終的には「大衆が歴史を作る」からである。
(アルチュセール「批判的・自己批判的ノート」市田良彦訳)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「六八年」の前年の文とはいえ、退いてしまうしかないフレーズが並んでいる。
一八四五年に「認識論上の切断」があったとして、その前とあとを明確に分けようとしても、その前後を通じてマルクスには貫かれるものがあったし、もちろんさまざまな揺れ動きもあった。「マルクス主義」という一直線などありはしない。
ただし、若いマルクスが心身深く受けとめた現実の社会への驚きと怒りは、生涯の活動の原点でありつづけた。
乱暴な「認識論上の切断」とともに、「労働における疎外のかたち」も葬られてしまったが、むしろわたしたちが今でも一日の主要時間力を注いでいる労働過程(生産過程、同時に相関する消費過程)を、改めてていねいに考察するべきだと思う。
(「マルクス」の項 続く)
(2011.5.11)
(c) M.Toyoda All Rights Reserved
|
 |