|
 |
| 「和風」原論 |
 |

追補
和風原論からの「経済学」批判 5
底の浅い「贈与」論 近代的思考の限界を露呈 |
〇「はじめに贈与ありき」
岩井さんは歴史の「原初」(『ヴェニスの商人の資本論』)に言及します。経済社会では等価交換があたりまえだが、その社会の原初には、等価交換の前提として不等価交換(一方的贈与)があるという。
「はじめに贈与ありき」と宣言します(同前)。
どういうことか。
たとえば、中央銀行が発行する銀行券(紙幣)は、他の債権と同じように、形式的には中央銀行の負債である。しかし、それは「決して返済する必要のない負債」である。形式的には負債であっても実質的には負債として機能しない。この事実には、一方的な贈与が隠されている、つまり国民から中央銀行(国家)への「一方的贈与」が。
金や銀が山から掘り出されるとき、山主は利潤を得ることなしには、採掘しない。炭鉱夫を雇って道具を揃え、金銀を採掘させるとき、道具機械を買ったり、さらに炭鉱夫に支払う費用総額以上の金銀を採掘する。そしてその金銀でモノを買うときに、それが貨幣として受け入れられたとき、超過分が利潤として実現する。このとき、金銀を貨幣として使っている人々から、山主にたいして、隠された一方的な贈与が行われている、というのが岩井さんのとらえ方だ。銀行券と同じように、不等価交換が前提とされている。
だから、「貨幣が貨幣として機能している背後に、必ず一方的贈与という不等価交換の契機(モメント)が介入している」ことになる。
この贈与、いいかえれば不等価交換、(搾取、剰余価値の創出)は、過去にだけみられたものではなく、貨幣が流通しているかぎり、未来にも見出される。
さて、岩井さんのいう「一方的贈与」では、銀行の銀行券(紙幣)では、国民から中央銀行へのそれであり、金山銀山での採掘では、金銀を貨幣として使う人から山主へのそれである。これらの一方的贈与は、国民から中央銀行(国家)へ、また金銀を貨幣として使う人から山主へのもの。つまり、人から人(あるいは組織)への贈与である。
贈与をこのようにしか捉えられないとき、近代的思考の限界がはっきり示されています。

○問われる根源的贈与
贈与はもっと根源的に考えられなければならない。人以外のものから人への贈与。
たとえば、山に埋もれた金と銀は、まず人間への一方的な贈与としてある。これは一端でしかありません。大気、大地、海、川、植物、動物、自然のすべてが、人間に対して一方的な贈与として存在している。利潤が生まれる元に、大地(自然)からの一方的贈与があることをうけとめざるをえない。
貨幣・「経済」が成立する前提に、自然からの贈与(大地、海、地球、宇宙、そして「私」という贈与)がある。
「はじめに、贈与ありき」と岩井さんは書きました。原初の(そして今も基底でありつづける)不等価交換、搾取による剰余価値があった、とも言い換えている。それを彼は人間世界内にとどめている。経済学の範疇から出ない。
しかし、もし「贈与」を語るなら、経済(経済学)を成立させているその前提としての不等価交換・いいかえれば贈与に降りなければならない。そこまで視線を伸ばすことが求められる。いや、自然・地球の限りが見えているいま、それは義務でなければならない。
岩井さんが経済学を語るとき、根源的贈与に触れずとも許されるでしょう。しかし彼は歴史の原初について触れ、贈与について語るのです。経済領域の外部に足を踏み入れている。
しかし残念ながら、岩井さんは存在論的に降りられないので、この根底的贈与に目が向けられない。
「貨幣が貨幣として流通しているのは、それが貨幣として流通しているからでしかない」(『貨幣論』)。こういう貨幣の自己循環論が成立するには、その基盤が存在する。自己循環を許してくれる土台がなければならない。しかし、その土台を問わない。カントと同じです。
この不等価交換(贈与)は、そもそも存在の生成に依存している。地球という土台であり、海、川、大気、そこに生息する動植物、それらに人間も依存している。
○悪しき「未来への先送り」
また岩井さんは、「未来への先送り」という表現を使っています。
「ここで重要なのは、貨幣を貨幣として維持していくこの未来への先送りが、文字どおりの無限の未来の人間への先送りでなければならないということである(同前)」。
あるいはこう言います。
「たんなる一枚の紙切れが、貨幣として使われているということによって、紙切れとしての価値をはるかにこえてもつことになる一万円という価値とは、無限のかなたの未来に住む人間から今ここに住む人間への送られてきた、気前のよい贈りものにほかならない」(同前)。
決済の先送り、負債の押しつけを一概に批判はできません。ただ、それを「未来に住む人間」からの「気前のよい贈りもの」と素直に喜んでばかりいられるでしょうか。
決済すべき負債が膨大になったとき、未来人は、「気前のよい贈りもの」という岩井先生の勝手な規定に抗議するにちがいない。「未来」の人の意向を勝手にでっちあげて、あたかも未来人からの贈与とするのは、現在の人間の都合のよい思いつきでしかない、と。
銀行券決済の先送りだけではない。とくに、使用済み核燃料の廃物の処理・保管・危険を押しつけられることを、「未来に住む人間」はよしとしてくれるのだろうか。今日に生きる人間の誰もが受けいれを拒否している核の廃物の受けいれの押しつけを、未来人からの「気前のよい贈りもの」と勝手に褒めちぎってよいものなのだろうか。
○大地の贈与を受けとめたワルラス
フランスの経済学者レオン・ワルラス(一八三四〜一九一〇年)は、人間と大地の関係について、根本的な問いかけをしている。
「彼(ワルラス――引用者註)は、土地の私有にはどのような正当性もないと考えたのである。土地は、神が人類に与えたものであるから、彼にとっては土地は、人民が共有すべきものであった」(森嶋通夫『思想としての近代経済学』)。
そのワルラスは、著書『純粹經濟學要論』で、土地について次のように書いています。
土地は自然的資本であって、人為的資本でもなく、また生産せられた資本でもない。また土地は消費し尽されない資本であって、使用により事変により消滅しないものである。だが岩石の上に土を運び、または排水灌漑等により人為的に生産せられた土地資本がある。また地震により河水の氾濫により滅失する土地資本もある。しかしこれらは少数であって、従って少数の例外を除けば、土地資本は消費し尽すことも出来ねば、生産することも出来ない資本であると考えてよい。これら二つの事情は各々その重要性をもつものではあるが、しかしこれらの二つの事情の同時的な存在が、土地資本にその特有な性質を与えるのである。すなわちこれによって、土地の量は厳密に一定不変ではないにしても、少くとも変化の少いものとなり、従って土地のこの量は原始的社会においては、すこぶる豊富であり、進歩した社会においては、人及び狭義の資本の量に比較してはなはだ限られたものとなる。その結果、事実において見るように、土地は、原始社会においては、稀少性も価値もゼロであり、進歩した社会においては、高い稀少性と価値とをもつものである。
(手塚壽郎訳 青空文庫より)
原始的社会では、土地は「すこぶる豊富」だった。しかし、次第に「はなはだ限られたもの」となる。「進歩した社会」では、「高い希少性と価値とをもつもの」となる。
そして、今日、新天地(フロンティア)は消滅しつつある。「高い希少性と価値」をもつ土地のありがたさを身に沁みて感じる段階を迎えたのです。皮肉なことに、フロンティアの消滅が、自然・大地が贈与としてあることを浮き彫りにしている。
ワルラスは二世紀も前に、すでに土地が贈与されたものであり、社会の「進歩」にしたがい「高い希少性と価値」をもつことになることをみていましたが、岩井さんは、フロンティアの消滅間近な現在でも、「無限の欲望」と「全き自由」追求のため、自己増殖を目的とする資本主義を守らなければならないと強弁しつづけています。
フロンティアが消滅した現代では、成長を追い求めれば追い求めるほど、民間企業は巨大な損失を被り、国家は秩序を失ってしまうのです。
(水野和夫『閉じてゆく帝国と逆説の21世紀経済』)

(2017.8.31)
(c) M.Toyoda All Rights Reserved
|

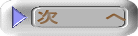
|
|

