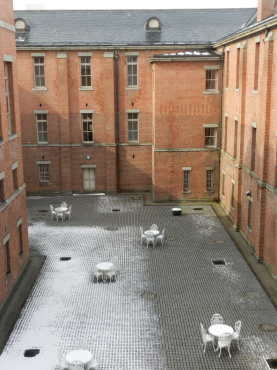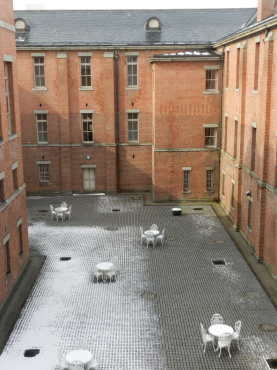|
 |
| 「和風」原論 |
 |
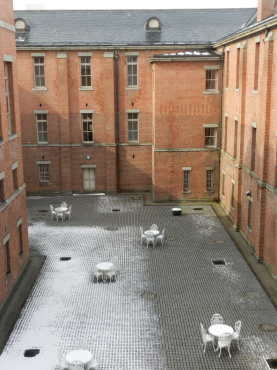
3 「人間主義」という袋小路
○「無限」に祀りあげられた人間
「人格が身体を所有する」という西欧的論理がいかに奇怪であるか。それを図らずも示したのが、「デカンチェ」の一人であるカント(一七二四〜一八〇四年)です。西洋の道徳哲学の最高峰を築いた人物です。
絶対の最高善を説くカントは、身体や自然を蔑視する西洋的思考の典型でした。覆うべくもない彼の論理の破綻について、触れておきます。
 彼は一八世紀後半から一九世紀はじめにかけて、ドイツ(プロイセン)で活躍し、ドイツ観念哲学の祖といわれます。いったい人間は「何を知ることができるのか」、「何をなすべきなのか」、「何を望むことができるのか」を、哲学の課題としました。 彼は一八世紀後半から一九世紀はじめにかけて、ドイツ(プロイセン)で活躍し、ドイツ観念哲学の祖といわれます。いったい人間は「何を知ることができるのか」、「何をなすべきなのか」、「何を望むことができるのか」を、哲学の課題としました。
カントはデカルトがいう「私は考える、ゆえに私はある」の、「私は考える」をさらに考察しました。一般に私たちは、人間(主観)が自然や対象をとらえるとき、まず自然対象があって、それを人間が認識する、と考えがちです。しかしカントによれば、人間(主観)は自分が認識できる対象を、ただ「自然」といっているにすぎない、というのです。つまり、人間が認識できる能力には限界がって、「もの自体」(ほんとうにあるはずのものそのもの)をとらえることはできない。人間の認識は完全でないことを認めました。
したがってカントは、ものごと、自然を認識するときは、「私たちにとっての」という限定を付けることを忘れませんでした。私たちが認識する対象は、あくまでも人間という主観がとらえたものでしかない。とらえられた対象は、限界をもつ主観に従っているにすぎない。だから人間の力では「もの自体」は認識できない。カントは人間(主観)の限界を謙虚に示したはずでした。デカルトを超えて「主観」の限界を強調しました。
ところが彼はいつの間にか、その「私たちにとって」という「限定付き」(条件)をとっぱらってしまいます。人間が関わるところにだけ自然は成りたっている、と認識を発展させます。その結果、人間は自分が関わる自然を支配できる、と幅を押し拡げました。神の前で有限であるはずの人間が、いつのまにか無限な存在であると考えるようになります。人間(主観)が自然を支配し操作できるとする近代の驕りは、カントによってさらに強く固められました。
たしかにカントは厳格な道徳哲学をうちたて、また世界平和を訴えました。
近代社会は国家間の争い、戦争が絶えない。カントは出現しつつある近代社会の問題点と真剣に向きあいました。私たちが生き、判断し、行動するとき、ほんとうに基準となる道徳とは何か、善とは何か、考えを突き詰めました。
お金を手にしたいとか、他人に評価されたいというような不純な動機が少しでもあったら善とはいえない、というのが彼の立場です。道徳心は、何か別のものを得ようとするための手段ではない。俗世の利益や感情や野望に左右されてはいけない。何々のために善を行うというのであれば、善が手段になってしまう、それでは真の道徳ではない。ただただ、ほんとうの善、理性に基いて実行されるのが、究極の道徳であると考えました。
また、他人(人間)を手段としてだけ扱うことを諫め、他人を目的として扱いなさい、と説きました。つまりもっとも尊重するべき存在として他人を扱うことが善であり、理性であると。私たちは仕事や日常生活で、どうしても他人を手段としてしまう。自分の利益や快楽を実現することが一番で、そのために他人をどう利用するか、と考えがちです。こういう傾向にたいして彼は、人間が「ほかの目的の手段としてだけ使われてはならない」と「人間の尊厳」を主張しました。欲望の実現をめざして互いに争う近代社会にあって、魅力をもつ道徳哲学です。
○「やられたら、やりかえせ」というカントの「道徳」
しかし、カントの哲学には隠しようのない大きな綻びがあります。それは彼の思考の基本に関わるばかりか、西欧近代思想の根幹にかかわるものです。
彼の哲学が破綻している例をひとつだけみておきましょう。
『人倫の形而上学』という本で、彼は法律と道徳の哲学について論じています。この中で結婚や、性の道徳的義務についても触れ、性的行為(性交)について考察します。
カントによると性的行為とは、まず人格が「生殖器」(性器)という身体の一部を「使用」するものだ、ととらえます(性的交流が「生殖器」(性器)という身体の一部だけを「使用」するものではないことは明らかですが、ここではその問題は省きます)。
「生殖器」は、人格が手や足を使うのと同じように、「使用」するものと彼はとらえます。性的交わりは、彼からみると、ある人が他の人と「生殖器および性的能力についてなす相互的な使用」となります。つまり「人格」が所有する自分の身体の一部である生殖器を「使用」することです。また、相手の身体の一部である生殖器を「使用」することなのです。これは、人格と身体が分かたれ、人格が身体を所有し支配する主人であるという前提から発想されます。
さて、この性的交わりは、カントによれば二つに分けられます。「動物的自然」、つまり欲望に従うだけのもの(「放蕩、相手構わぬ淫乱、売春」)か、あるいは、理性的「法則」に従うもの(婚姻)か、のいずれかです。彼によると、結婚とは「性的特性を生涯にわたって相互に占有する」ことになります。もし「使用」、「占有」したい欲望をもつなら、結婚する以外にありません。
私がここで問いたいのは結婚観ではありません。性的行為が道徳として容認される条件なのです。カントの厳格主義的な四角張った表現を、私なりに読み解いてみます。
ある人が相手の生殖器を「使用」するのは、「享楽」、快楽目的であり、相手に「身を任せる」のは、自分を「物件」(つまり「もの」)として相手に差し出したことになる、というのです。たんにものを相手に提供しているだけです。それでは、身体の一部(生殖器)を提供した人は、人間ではなく、物件(もの)と化してしまい、「人間性」を喪失する。それは人間性の権利に反する。人間は「もの」ではないからです。とすれば、相手の生殖器の「自然的使用」(「享楽」)は、人間性に反するので認められないことになるはずです。
でも、とカントは苦しまぎれに次のように考えました。それが許される条件が、ひとつだけある、というのです。逆転の切り札がある、と。たしかに、人が相手の快楽目的のために、自分の生殖器を「自然使用」されてしまえば、自分が「もの」として扱われたので、人格、人間性が否定されます。でも、その人が、自分を物件(「もの」)として扱った相手を、同じように「もの」として「取得」すればよい。そうすれば、自分の「人格性を回復」できる。つまり、自分が「享楽」の主体となって相手を物件として扱えば、人格としての自分を取りもどせる、というのです。
はじめは、たしかに相手に生殖器を「使用」され、自分が物件として相手に「取得」されてしまい、人格を損なわれた。しかし、今度は逆に自分が相手を「取得」してしまえば、人格性を回復できる、というわけです。俗っぽくひとことでいえば、「やられたら、やりかえせ」の流儀で自分の尊厳が保たれる、というのです。
しかし、相手の生殖器を「使用」「取得」することによってしか、人格が回復できないというカントの論理は、裏を返すと「人格」が「身体」に支配されている証左にほかなりません。支配しているつもりが、支配されているのです。そのことにカントは気づきません。
○カントの傲慢
 もともと、「使用」や「占有」、「取得」といった法的概念とは結びつかない性的交流が、彼の法・道徳論の場では、「やられたら、やりかえせ」といった喧嘩の様相を呈します。相手の性器を「使用」したか否か、相手を「占有」したか否か、相手の権利を奪ったか否か、という貧しい、かなり矮小化された世界になっています。そこに、互いの心身の交流と広がりという豊饒の世界はまったくうかがえません。 もともと、「使用」や「占有」、「取得」といった法的概念とは結びつかない性的交流が、彼の法・道徳論の場では、「やられたら、やりかえせ」といった喧嘩の様相を呈します。相手の性器を「使用」したか否か、相手を「占有」したか否か、相手の権利を奪ったか否か、という貧しい、かなり矮小化された世界になっています。そこに、互いの心身の交流と広がりという豊饒の世界はまったくうかがえません。
背景には、古代からの奴隷制への批判もあったし、クリスチャンとしての制約もあったことでしょう。法や道徳、人倫の中に結婚と性の問題を位置づけようとした必死さはうかがえます。それにしても、これは「学」の戯言にすぎません。
たしかに、哲学や思想、芸術は、その時代の深い影響を受け、時代の制約を刻まれます。どんなに素晴らしい思想や哲学、理念であっても、反面、弱点や欠陥を抱えているものです。それをあげつらうよりは、優れたところをみつけ、学ぶことが求められます。とはいうものの、人間のあり方の根幹に関わる性的領域が、「やられたらやりかえせ」で辻褄合わせされることを見逃すわけにはいきません。
「人格が身体を支配する」という近代哲学の破綻です。他人を手段としてではなく目的として遇するように、と呼びかけておきながら、性の領域では、身体(性器)を「使用」され「もの」として扱われたら、同じことを他者にやり返してものとして扱えば、人格を回復できるという、とんでもない発想に陥っているのです。
カントや西欧的理性にとって、身体は邪魔ものでしかありません。人間の本質は理性、人格にあり、身体を所有し、支配しなければならない、そこにこそ人間の「自由」と「尊厳」があり、「理性」が発揮できる。身体や自然を徹底し蔑視、あるいは否定します。そういう西欧的二元論の破綻がカントにもはっきり露呈しています。
そもそも人格と身体とは二分できません。人格と身体は、「所有する」・「所有される」の一方的な関係に収まりません。人格が身体を所有するという「人格・理性の驕り」のもとでは、自分が存在していることに「かたじけなさ」を感じることなど到底ありえません。
こういうとんちんかんな論が真面目に展開されているところに、西欧近代哲学・道徳思想の矛盾が露わになっています。
(2016.2.2)
(c) M.Toyoda All Rights Reserved
|


|